広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ
広島市中区大手町3丁目11-19
082-241-8610
後遺障害の調査と認定手続き

交通事故では、けがをして長期にわたり治療を続けても、症状の改善がみられず後遺症として残ってしまうことがあります。
1.治療終了(症状固定)になり、体に事故
による障害(違和感)が残った場合は、
「後遺障害等級認定」という手続きに入ります。
① 症状固定後は、後遺障害が認定になれば自賠責保険では、その等級に対 する保険金額が1級から14級までそれぞれ定められています。
② 任意保険では、等級ごとの上限はなく、保険金額の範囲内で法律上の損 害賠償責任額が対象になります。
従って、個別に、後遺障害等級の逸失利益および後遺障害慰謝料を計算 することになります。
2.「症状固定」とはこれ以上治療を継続しても、治療効果が見込めないとい
う意味で、「等級認定」は、症状固定時に体に残っている支障にランクを つけるものです。
① 症状固定は、保険会社からあるいは担当の医師から言われますが、まだ 治療効果がある場合や本人が良くなっている実感がある場合は、遠慮なく医 師に伝えることが大切です。
② ただし、傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復が みられるに過ぎない場合は、症状固定として後遺症と考え、後遺障害等級認 定に移ることがあります。
③ 症状固定日までが、交通事故による「傷害」部分の損害賠償の対象と期 間で、この日以降はこの症状が後遺障害の等級に認定されれば「後遺障害」 部分として損害賠償の対象となります。
後遺障害が「非該当」になれば、当然、この日以降は損害賠償の対象にはな りません。
④ 後遺障害の等級が一つ違うだけで逸失利益と慰謝料の額がかなり異なり ますので、正当な等級を得るための知識と事前準備は非常に重要なポイント となります。
↑
行政書士や弁護士に相談や業務依頼をする一番のメリットは、ここの
「後遺障害等級の獲得」部分です。
⑤ 注意すべきは、いくら本人が自覚症状を訴えている状況でも、短期で通 院が途絶えていたり、無断で接骨院ばかり通っていれば、どんな専門家でも 有効な資料は揃えられず、「非該当」になる可能性が高くなるということで す。
保険会社からの提示や症状固定時点よりも早い時期に、専門家のアドバイス を受けることが大切だと思います。
3.交通事故の後遺症の請求方法には、事前認定と被害者請求の2種類があり
ます。
① 事前認定
加害者が任意保険に入っている場合に、その保険会社からの照会によってなされる等級認定のことです。
(加害者の)任意保険会社
(全ての診断書・画像等を提出)
⇓
損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)
⇓
(加害者の)任意保険会社
(等級認定決定あるいは非該当の通知)
(保険金・示談の打診)
⇓
被害者
② 被害者請求
被害者が相手側の自賠責保険会社に直接請求してなされる等級認定のことで
す。
後遺障害の部分については、傷害部分を任意保険会社が対応している場合で
も、被害者請求の形で直接、自賠責保険会社に等級認定を請求できます。
被害者 (あるいは行政書士事務所が代行)
⇓
(加害者の)自賠責保険会社
⇓
損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)
⇓
(加害者の)自賠責保険会社
(等級認定決定あるいは非該当の通知)
⇓
被害者
後遺症の(保険会社による)事前認定
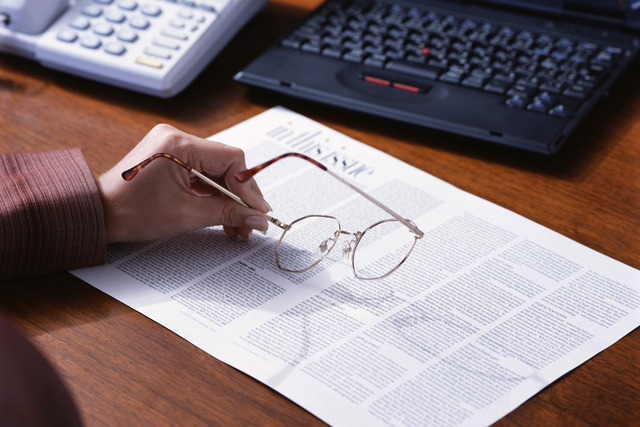
1.事前認定は、加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出して、その保険会社から損害保険料率算出機構に申請してもらうという方法です。
2.任意保険会社に手続きを一任することで
被害者の負担は軽くなり、かなり多くの方がこの方法で示談をされています。
(事前認定の短所)
① 等級認定は書類審査ですが、被害者は保険会社が認定機関にどういう資料 を提出したか、その資料の内容はどうかなどをチェックできません。
⇓
つまり、原則として被害者本人と調査事務所の担当者との面接はないので、 本人の現状を訴える手段はなく、それだけ提出資料が重要になるということ です。
② 後遺症を認定するための必要な資料が不足して、認定機関が実際よりも低 い評価を出す可能性があります。
⇓
基本的に、損害の立証責任は被害者側にあり、加害者側は被害者の後遺症が どれだけ重いかを立証する義務はない、ということを知っておく必要があり ます。
③ 最悪の場合には、資料が適切でないため、「非該当」となるかもしれませ
ん。
④ 一般の方は、保険会社からの正式通知に威圧されて、その結果が正当で不 変のものであると思いがちになります。
⑤ 保険会社が支払いを低く抑えようという方針であれば、保険会社の顧問医 師がそれに沿った意見書を添付する可能性もあります。
⑥ 任意保険会社との示談交渉が成立しないと、自賠責保険部分も含めて補償 を受け取れません。
⑦ 任意保険会社が、自賠責保険の賠償部分を除いて、いくら支払ったのかが わかりません。
後遺症の被害者請求

1.被害者請求は、被害者が自分で必要書類
をそろえて自賠責保険会社に直接申請する方法です。
2.この方法ですと、自分で後遺症認定に必
要な資料を提出できるため、認定結果に納得できます。
3.また、後遺障害等級が認定されると、自賠責保険会社に通知され、相手側
の任意保険会社との示談を待たずに、自賠責保険会社から損害賠償金が等級認定に応じてすぐに支払われます。
(被害者請求の短所)
⇓
(交通事故を扱う行政書士に依頼すれば、下記の問題はほとんど解決します)
1.自分で提出書類を調べてそろえ、適正な内容となるように動かなければな
らず、負担がかかります。
2.自賠責保険会社も、被害者や行政書士からの診断書コピー等の要請に対し
ては、冷たい態度をとります。
3.診断書や補足資料の内容の意味が把握できなければ、自分でそろえるメリ
ットがなくなります。
4.診断書の記載ミス・記載もれをチェックするだけでも、かなりの知識が必
要となります。
後遺障害認定の申請(被害者請求)
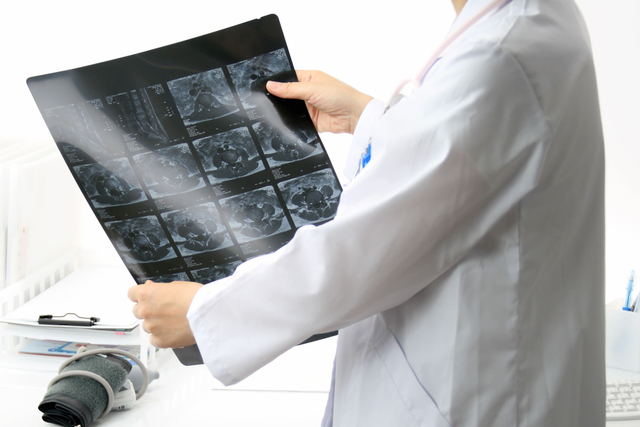
 後遺障害認定の申請手順は、次の通りで
後遺障害認定の申請手順は、次の通りで
す。
1.後遺症の立証に必要な検査の実施や後遺
障害診断書の医師所見について、医師との面談や文書照会によって、確認したり必要な検査の依頼を行います。
⇓
2.申請書類一式を作成します。
(提出書類)
① 後遺障害診断書
② その他の診断書
③ 診療報酬明細書
④ 施術証明書
⑤ 施術費明細書
⑥ 診断画像 (レントゲン・CT・MRI)
⑦ 神経学的所見
⇓
3.自賠責保険会社に申請します。 等級認定を得るために最も必要なものは、客観的な医学的証明です。
等級認定を得るために最も必要なものは、客観的な医学的証明です。
医学的証明というのは、本人の自覚症状ではなく、他覚的検査によって証 明できるということです。
特に、体の表面の傷ではなく、目に見えにくい後遺症の場合は、それぞれ の症状に合った検査結果の証明が必要となります。
⇓
必要な書類として、次のようなものがあります。
① 後遺障害診断書の「自覚症状」欄の正確な記載
② 画像所見(X線写真・CT画像・MRI画像)
③ 神経学的検査による異常所見 主な後遺障害として、次のようなものがあります。
主な後遺障害として、次のようなものがあります。
① 頸椎捻挫(むち打ち症)・腰椎捻挫
② 頸椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折
③ 関節機能障害
④ PTSD(心的外傷後ストレス障害)
⑤ 高次脳機能障害 後遺障害等級の慰謝料基準
後遺障害等級の慰謝料基準
1.参考資料として、「後遺障害慰謝料」金額の3つの基準を示します。
(*入院・通院時の慰謝料については、別に詳細なマトリックス図があります)
2.① 自賠責保険基準の保険金総額は、慰謝料と逸失利益の総額です。
② 任意保険基準は、保険会社の内部基準で、現在は各社一律ではなく、自 由に設定できるものとされています。
③ 裁判基準は、実際に裁判を提起あるいは想定した場合に認められる基準 で、最も高額となります。
3.①「労働能力喪失率」は、逸失利益を出すための、計算式の基準です。
② 逸失利益の計算式は、
「年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です
③ 例えば、年収400万円の40歳の会社員が、後遺障害11級に認定された場 合は、(就労可能年数は、67歳ー40歳=27年)
「400×0.20×14.643=1171万4,400円」が逸失利益となり、11級の自賠責保 険金額は逸失利益と慰謝料を合わせた総額でも上限331万円ですから、その差額 840万円は任意保険から支払われることになります。
④ 専業主婦の場合でも、賃金センサスにより収入の減少を算定されます。
⑤ むち打ち症の場合は、労働能力喪失期間は、14級で5年、12級で10年と されるのが一般的です。
4.① 下表の金額でもわかるように、後遺障害に該当する可能性があれば、 手間を惜しまず客観的根拠となる資料を長期的に集めて、正当な金額を得る 努力をすることが大切だとわかります。
等級が一つ違うだけで、50万円から数百万の差が出てきます。
② 保険会社も係争や裁判は避けたいので、過去事例から正当と思われる等 級・金額を提示すると思われますが、被害者のために親身になって根拠資料 を収集することはありません。
③ 3つの基準で、裁判基準が最も高額なのは一目瞭然で、この金額をめざ して交渉される方もいますが、この基準であれば、時間と労力と多額の弁護 士報酬を覚悟する必要があります。
| 等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 (一例) | 裁判基準 | 労働能力喪失率 | |
| 慰謝料 | 保険金総額 | ||||
| 1級 | 1100万円 | 3000万円 | 1300万円 | 2800万円 | 100% |
| 2級 | 958万円 | 2590万円 | 1120万円 | 2370万円 | 100% |
| 3級 | 829万円 | 2219万円 | 950万円 | 1990万円 | 100% |
| 4級 | 712万円 | 1889万円 | 800万円 | 1670万円 | 92% |
| 5級 | 599万円 | 1574万円 | 700万円 | 1400万円 | 79% |
| 6級 | 498万円 | 1296万円 | 600万円 | 1180万円 | 67% |
| 7級 | 409万円 | 1051万円 | 500万円 | 1000万円 | 56% |
| 8級 | 324万円 | 819万円 | 400万円 | 830万円 | 45% |
| 9級 | 245万円 | 616万円 | 300万円 | 690万円 | 35% |
| 10級 | 187万円 | 461万円 | 200万円 | 550万円 | 27% |
| 11級 | 135万円 | 331万円 | 150万円 | 420万円 | 20% |
| 12級 | 93万円 | 224万円 | 100万円 | 290万円 | 10% |
| 13級 | 57万円 | 139万円 | 65万円 | 180万円 | 9% |
| 14級 | 32万円 | 75万円 | 40万円 | 110万円 | 5% |
 後遺障害等級の併合
後遺障害等級の併合
1.例えば、同一交通事故によって膝の関節と眼球に後遺障害が2つ以上残っ てしまった場合、それぞれの該当等級を基準に従って1つの等級で認定する ことを、等級の併合といいます。
2.併合の取り扱いは、原則として重い方の身体障害の等級で認定します。
⇓
・例えば、「13級以上に該当する後遺障害が2つ以上の場合は、重い方の等級を1級 繰り上げる」というような細かな基準が示されています。
3.併合による保険金の計算は、併合前のそれぞれの等級の保険金の合計額と 併合後の保険金額を比較し、小さい方の金額を保険金とします。
⇓
・例えば、9級と13級の2つは併合によって8号になりますが、9級(616万)+13級 (139万)の合計額755万と8級の819万を比較し、併合8級であっても保険金額は少ない 方の755万円となります。
後遺障害認定の異議申立て(再請求)

後遺障害認定結果に対して納得できない場合、異議申立て(再請求)をすることができます。
この場合は、保険会社の事前認定でも被害者請求の結果でも、再請求をすることができます。
その場合、新たな医学的証明や検査を行って正確な症状の証明を補足する必要があります。 異議申立てについても、申請手順自体は、等級認定の申請と同じです。
異議申立てについても、申請手順自体は、等級認定の申請と同じです。
1.後遺症の立証に必要な検査の実施や後遺障害診断書の医師所見について、
医師との面談や文書照会によって、確認したり必要な検査の依頼を行いま
す。
⇓
2.申請書類一式を作成します。
(新たな資料の添付)
⇓
3.① 被害者請求の場合は、加害者加入の自賠責保険会社に申請します。
② 事前認定の場合は、加害者加入の任意保険会社へ提出します。 この申請については、新しい医学的証明を添付しなければ、ほとんど認め られません。
この申請については、新しい医学的証明を添付しなければ、ほとんど認め られません。
最初の申請と同じ書類を提出しても、当然結果は同じになるわけですから、該当する等級の認定基準を理解し、医学的な観点から分析することが必要になります。
そして、その分析が診断書あるいは医師の意見書に反映されて、異議申立て申請の書類として提出されなければなりません。
保険会社・調査事務所の判断が間違っているのではなく、当方の提出書類が不十分だから等級認定が受けられなかった、という意識で検討することが必要でしょう。
従って、後遺障害等級の異議申請をする場合も、担当医師に認定ポイントの意見書ないし診断書をお願いすることになるので、治療の最初の段階から良好な関係を保っておきます。
また、単に口頭でお願いするのではなく、忙しい医師が的確に書類に記入してくれるよう事前準備の記入要領的な書面や家族の被害者日常行動記録などを提出することが大切です。 1.異議申立てを検討するケース
1.異議申立てを検討するケース
① 後遺障害の診断自体が不十分
② 後遺障害診断書の記載が不十分・不適切
③ 必要な検査の未実施、検査方法が不適切
④ 被害者の症状の特別な事情が未記載
⑤ 併合する部位が未記載




