広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ
広島市中区大手町3丁目11-19
082-241-8610
相続人の調査・確定と戸籍収集

ここで、相続人の調査・確定と戸籍の収集について説明します。
1.遺産相続の手続きでは、必ず戸籍謄本や除籍謄本などが必要となりす。
それは、相続が発生したときには、まず「相続人の確定」をする必要があるからです。
2.そのために、亡くなった方本人の出生から死亡までのつながった除籍謄本
・改製原戸籍・戸籍謄本を取り寄せて相続人を調査します。
通常、出生後は親の戸籍に入ります。その後、引越し時に転籍したり、結
婚して新戸籍になったり、または法改正で戸籍が改製されたりと戸籍の変遷があるので、それらすべてが必要になります。
これらの戸籍によって、被相続人(亡くなった方)と相続人を判断します。
また、銀行などの諸手続きにおいても、相続人であることの証明のため、提出を求められます。
3.これらの除籍謄本などを慎重に照らし合わせて、「相続関係図」を作成しますが、この相続関係図も遺産分割協議書とセットにして提出するので、重要になります。
4.普段、ご自分の住民票や印鑑証明書の請求は、市役所や区役所で慣れていても、除籍謄本などは請求されたことがないかもしれません。
特に最近は、個人情報や不正取得防止の趣旨から、住民票でも、同居している親子でも世帯を別にしていれば、委任状を書いてもらって請求しなければ受け付けてもらえない時代になり、本人確認も役所によって要求される書類が違いますので、よけいに神経を使います。
5.相続人の確定には、民法の規定する相続人の順位と相続割合を知っておく必要があります。
遺言がある場合は、指定相続人が明記されていますから、こちらが優先します。
各謄本の種類

① 除籍謄本
戸籍に記載されている方が、死亡や婚姻、
離婚、養子縁組、分籍、転籍(本籍を変え
る)などによって他の戸籍に移った場合、
戸籍に関する記載や情報処理がされなくな
りますが、このような全員除籍によって抜
け殻になった戸籍をいいます。
② 改製原戸籍謄本
法令改正によって戸籍が新しい戸籍簿に書き換えられた際の、書き換え前の
戸籍をいいます。(現戸籍と区別するために、俗に「はらこせき」と呼ばれ
ます。)
原戸籍は2種類あります。
1つは、戦後に明治以来の「戸主」を中心とした戸籍を、夫婦中心に改め
ましたが、その夫婦中心に改める前の戸籍を、「昭和改製の原戸籍」とい
います。
2つめは、従来紙の戸籍簿で戸籍事務を行っていたものを一定の日(改製
日)以後コンピューターによって入力することになりましたが、そのコン
ピューター化する前の戸籍を、「平成改製の原戸籍」といいます。
③ 現在の戸籍(戸籍全部事項証明書)
平成6年に戸籍法が改正され、以前の縦書きからデータ化された横書きA4
サイズで出力される戸籍です。
現在の身分関係(親子・夫婦)や、人物の状況(現在の氏名や性別、生年月
日)を証明するもので、通常夫婦と未婚の子供で構成されており、住所を表
すものではありません。
④ 戸籍の付票
住所(住民票)の移動が記録されているもの。
住民票の場合は、除票になってから5年ぐらいしか保存されないので、古
い権利書などの住所と一致させるためには戸籍の付票を利用します。
戸籍収集のポイント
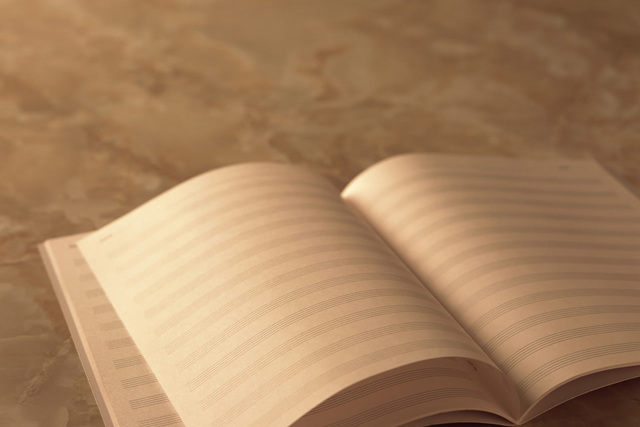
① この戸籍収集で面倒なのが、住民票と違
って本籍のある役所でしか取得できないので、遠方であれば郵送での取り寄せになることと、転籍や何回も再婚をしている場合は、各役所にそれぞれ請求しなくてはならないことです。
② 本籍のある役所の窓口での請求は、戸籍交付請求書・本人確認書類・手数料・代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
郵送の場合は、手数料分は定額小為替を購入して送付します。
③ 昔と違い現在は、交付請求書は役所などのホームページでダウンロードができ、返送される日数も驚くほど短縮されました。
二度手間を避けるためには、必ず事前に役所の窓口に電話をして、具体的に「何のためにどういう戸籍が必要か」、「本人確認書類は免許証か健康保険証か、どのコピーでいいのか」、「封筒の中には、定額小為替の他何を同封すればいいのかを、確認することが大切です。
④ 戸籍を取り寄せて困惑するのが、特に昔の縦書きの除籍謄本を見るのが初めてという場合に、旧字体で達筆で書かれているために、解読に苦労することです。
また昔は、家督相続などの理由で、分家や養子縁組がよく行われており、親から詳しい事情を聞いていない場合は、戸惑うこともあります。
⑤ 故人の出生から死亡までのつながった戸籍を全て取り寄せるわけですから、故人本人の分だけでも人によっては5~6通、相続人が10人近くなるとすべての相続人に依頼し、それを代表者が集めてコピーもするという、結構面倒な作業になることもあります。
⑥ 相続人が配偶者と子供で確定すれば楽ですが、配偶者がいない場合や、配偶者のみで、被相続人の親(直系尊属)や兄弟姉妹も関係してくる場合は、調査に手間と時間がかかるのが普通です。
⑦ ⑥の場合に例えば、除籍謄本に離婚の記載や配偶者の死亡の記載がある場合、配偶者はいないことになります。
しかし、子・兄弟姉妹の有無は、相続開始の戸籍(除籍謄本)だけでは判明しないことがあります。
故人が過去に婚姻・離婚をし、その後本籍を移転した場合では、故人の除籍謄本には、その前婚に関する記載はありません。
戸籍の身分事項欄の記載は、新戸籍が編製された、他の戸籍に入籍したあるいは本籍を移転した場合は、移記されない事項があります。
従って、被相続人の除籍謄本のみでなく、転籍前の戸籍(除籍謄本)、改製原戸籍等、被相続人の出生に遡って戸籍を請求し、子がいるかどうか兄弟姉妹はいるかなどを確認する必要があります。
⑧ 自分で戸籍の解読や相続関係図を作成するのが少し心配だという方は、取引のある金融機関や行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。
相続人の範囲

相続人の範囲は、民法によって決められて
います。
《1》遺言がない場合は、民法で定められ
た割合に基づいて相続分が決定されます。
これが、「法定相続分」です。
大きく分けて「血族相続人」と「配偶者相
相続人」があり、その定められた範囲の人だけが相続人となります。
《2》被相続人が遺言書をのこした場合は、原則としてその遺言書で示され
れた割合が優先します。
これが、「指定相続分」です。 (相続人と法定相続分とは)
(相続人と法定相続分とは)
① 戸籍上の配偶者は、常に相続人になります。
② 配偶者が死亡していれば、法定順位に従い血族相続人が相続します。
① 配偶者のみが相続人であれば、配偶者がすべて相続します。
(子供も親も兄弟もいない場合)
| 配偶者 全部 |
② 子供がいれば、配偶者と子供が相続人です。 (第1順位)
子供が先に死亡していれば、孫が代襲相続によって引き継ぎます。
孫以降も代襲が続くことが、おい・めいまでで終わる兄弟との違いです
実子も養子も、相続分は同じです。
| 配偶者 1/2 | 子 1/2 |
③ 次に、子供がいなければ、親または直系尊属(祖父母)が相続人です。
(第2順位)
| 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |
④ 子供も親もいなければ、兄弟姉妹が相続人です。 (第3順位)
兄弟姉妹が先に死亡していれば、その子供のおい・めいが代襲相続によ
って引き継ぎます。
| 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
⑤ 配偶者がおらず、子供だけであれば、子供が全て相続します。
| 子ども 全部 |
⑥ 配偶者・子供がおらず、親だけであれば、親が全て相続します。
| 親 全部 |
⑦ 配偶者・子供・親がおらず、兄弟姉妹だけであれば、兄弟姉妹が全て
相続します。
| 兄弟姉妹 全部 |
 (相続欠格と相続廃除とは)
(相続欠格と相続廃除とは)
1.「相続人の欠格事由」とは、被相続人を故意に死亡させて刑罰を受けた
り、遺言書を偽造したりした場合に、相続人となる権利を失うことをいい
ます。
2.「相続人の廃除」とは、生前に被相続人が、後に相続人となる「推定相
続人」から暴力や侮辱などの著しい非行を受けていたような場合に、被相
続人はその者の相続権を認めないよう、「相続人の廃除」を家庭裁判所に
申立てたり、遺言で明記することができます。
家庭裁判所に申立てた場合は、相続の廃除を受けた者は、戸籍にその旨
が記載されます。
 (代襲相続とは)
(代襲相続とは)
1.「代襲相続」とは、法定相続人となるべき人が、被相続人よりも先に亡
くなっている場合(ex.親よりも先に子供が死亡)や、相続欠格や相続廃
除によって相続人が相続権を失った場合に、「法定相続人となるべき人の
子供」が相続人になることをいいます。
父ー子ー孫で、被相続人である父が亡くなった場合の、孫をいいます。
2. ただし、子が相続放棄をした場合は、孫は代襲相続の権利はありませ
ん。
3.法定相続人となるべき人が被相続人の子どもであった場合は、「孫」・
「ひ孫」などの下の世代に代襲されますが、被相続人の兄弟姉妹であった
場合は、兄弟姉妹の子どもである「おい・めい」までに限られます。
4.また、法定相続人となるべき父または母が亡くなっており、祖父母が健
在であるといった場合、祖父母は代襲しません。




