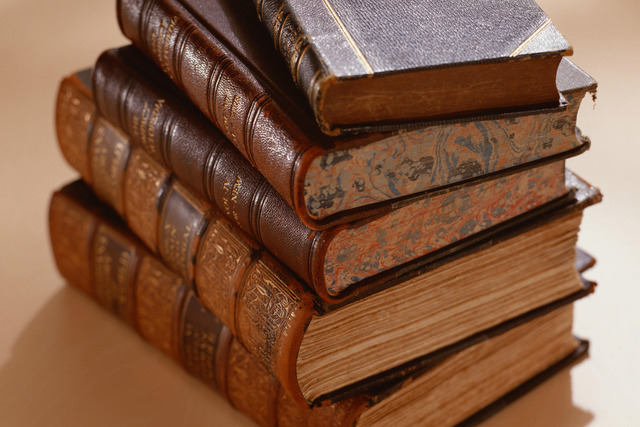広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ
広島市中区大手町3丁目11-19
082-241-8610
協議離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合い、合意ができれば成立する離婚のことです。
合意ができたら、市町村役場に離婚届を提出します。離婚の理由がなくても、どんな離婚理由でも、特に問われることはありません
ただし、未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらかを親権者として指定して記載しなければ、離婚届は受理されません。
(離婚の場合に、協議すべき項目)
① 離婚するかどうか
② 財産分与をどうするか
③ 慰謝料をどうするか
④ 履行の確保をどうするか
⑤ 復氏はどうするか
(子どもがいる場合)
⑥ 親権者をどちらに指定するか
⑦ 監護についての指定
⑧ 養育費をどうするか
⑨ 子供との面接交流をどうするか

(協議離婚の注意点)
1. このように、協議離婚は調停離婚や裁判離婚と異なり、夫婦が合意して離婚届を提出するだけですから簡単な手続きですが、もし養育費や財産分与で話しがついていたとしても、それが必ず将来にわたって実行されるとは限りません。
2.円満に離婚して、何も約束しないのであれば文書も必要ないですが、約束
をしたのに文書も交わさず、まして公正証書を作成しないという夫婦は多くいます。
3.夫婦の一方が、不本意ながら離婚に合意させられ、しぶしぶ何かの支払を
約束したとしても、そのような人が誠意をもって長期間支払いを行うことはあまり期待できません。
4.特に子供の養育費については、長期間分割で支払うことがほとんどですの
で、様々な事情の変化によって、途中で支払が止まるというのは十分可能性があります。

(離婚協議書のメリット)
離婚協議書の作成は、労力や費用がかかります。
しかし、それによって支払いを受ける側は、ご自身の生活費や子供の教育費の保障を得ることができるし、支払う側もこれから先の支払への責任を自覚しつつ、将来、不測の事態が生じた際の負担の軽減を明記しておけば安心できます

(協議内容を確実にするために)
1.将来、不測の事態になった時に有効なのが、公正証書を作成してもらう方法です。
2.「執行認諾条項」を付した公正証書を作成しておけば、もし養育費が滞っても、裁判の結果を待たずに強制執行が可能で、相手の給料などにも差押えをすることができます。
これは、相手側により強い責任感を持たせることにもなります。
3.公証役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印で押印し署名します。
そして、原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されます。
離婚協議書の項目と留意点

1.慰謝料・財産分与・養育費は、それぞれ科目を分けて算定することが通常です。
特に、養育費と慰謝料・財産分与は、別個の法律行為であり、時効の有無や強制執行できる範囲なども異なります。
養育費には、時効はありません。
2.また養育費には、不履行時の強制執行につき特例があり、給与所得等の定期収入の2分の1まで差し押さえることができます。
財産分与については、預貯金と現金など、同等額で相殺をすることができます。
3.しかし、慰謝料は財産分与と異なり、相手から一方的に相殺をされることのない債権です。
後あと面倒にならないよう、慰謝料・財産分与・養育費については、できる限り個別に金額を明示しておく方が安心です。
4.不動産など、金銭以外の現物での給付については、所有権移転登記手続きの履行期限などを明確に定めておくことが大切です。
そうしないと、期限の定めのない債務となり、万が一不履行となった場合など、手続きが面倒になります。
また、登録免許税などの費用負担を誰がするか、なども明確に定めておくことが大切です。

 財産分与
財産分与
1.財産分与とは、婚姻中に作り上げた夫婦の財産を離婚に際して清算・分配することで、その法的性質や要素には、次の3つがあります。
① 生産的財産分与
婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を清算・分配するもの。
一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相続などにより相手方に無関係に取得した財産は特有財産として除かれます。
② 扶養的財産分与
離婚後、一方の配偶者の収入や財産が少なく、生活が維持できないような場合に、資力のある相手方に分配を求めるもの。
③ 慰謝料的財産分与
離婚慰謝料については、財産分与に含めることができるが、別途、慰藉料のみを請求することもできます。
2.離婚をした者の一方が、相手方に対して財産の分与を求める権利を「財産分与請求権」といいます。
財産分与について、離婚時に合意に至らなかった場合や決めていなかった場合は、その請求は離婚の時から2年以内に行う必要があります。
3.財産分与によって取得した財産には、原則として贈与税はかかりません
しかし、社会通念上の許容範囲を大きく超えるような財産分与は、贈与税が課せられる場合があります。
また、不動産を取得した場合は、譲渡取得税が課せられる場合があります。
 慰謝料
慰謝料
1.配偶者の一方の有責行為によって、やむを得ず離婚に至った場合、これによってこうむる精神的苦痛に対する金銭的賠償を慰謝料とし、その請求が認められています。
従って、配偶者の不貞行為、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければなりません。
単なる性格の不一致で離婚する場合には、慰謝料請求権は発生しません
2.また、精神的苦痛の程度は個々人によって異なり、また離婚に至る経緯も千差万別なので、慰謝料額について客観的基準を明確に定めることは困難とされ、従って請求する金額にも決まりはありません。
一般には、① 有責性、② 婚姻期間、③ 相手方の資力 などを考慮する場合が多いようです。
3.慰謝料は、離婚に伴う場合は、通常、離婚の時から3年以内に請求する必要があります。
4.配偶者の不貞行為によって夫婦関係が破たんした場合には、配偶者とその第三者について共同不法行為が成立し、2人が連帯して損害を賠償する義務を負います。
従って、配偶者のみならず不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することができます。
 復氏
復氏
(1) 夫または妻の氏
1.婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。
そして、離婚の日から3ヶ月以内に届出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。(婚氏続称制度)
2.つまり、婚姻前の氏に復するか(旧姓に戻る)、婚姻中の氏をそのまま称するかを選択することができます。
これは、氏が変わることで、生活上の呼称をはじめ様々な変更が必要となり、社会生活上の不利益を受けることが少なくないからです。
3.復氏する(旧姓に戻る)場合は、婚姻前の戸籍に入籍することもできるし新戸籍を作ることもできます。
ただし、婚姻前の戸籍が除籍されているような場合(父母ともに死亡している場合)は入籍できないので、新戸籍を作ることになります。
(2) 子の戸籍と氏
1.離婚によって父母のどちらかが婚姻前の氏に改めても、子の戸籍はそのまま婚姻前の戸籍にとどまるため、子と復氏した父または母とは民法上の氏が異なることになります。
2.同居している親と子の氏が異なると、社会生活上様々な不都合が生じますその場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。
3.復氏した父または母が婚姻時の氏を続称している場合は、呼称上の氏は子の氏と同じですが、この場合でも民法上の氏は異なると解され、同じく「子の氏の変更許可申立て」の手続きが必要となります。
そして、「子の氏の変更許可の審判書の謄本」を添付して、入籍届を提出することによって、子の氏の変更ができます。
 親権と監護権
親権と監護権
1.「親権者」とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです。
この権利義務のうち、養育・監護に関するものを「身上監護権」、財産に関するものを「財産管理権・代理権」とよびます。
2.婚姻中の夫婦は、双方が親権者としてこれらの権利と義務を負い、共同親権者となります。
しかし離婚に際しては、親権者をどちらか一方に決めなければなりません。 (民法819条)
3.監護権は、親権のうちの養育保護、すなわち子の心身の成長のための教育及び教育を中心とする権利義務をいいます。
つまり、未成年者の子を監護・教育して一人前に育て上げる義務なのです。
本来は親権の一部ですが、離婚に際しては、これを分離して親権者と監護権者を別々に定めることもできます。
4.ただしこの場合の監護権者は、子の代理権を持たないので、子の氏の変更や各種手当の申請などで親権者の協力が必要となり、離婚後協力を得られる関係でない場合は、何かと不自由を生じるため、慎重に決める必要があります。
 養育費
養育費
1.養育費とは、未成熟な子供が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。
子供の生活に欠かせない食費や教育費その他の生活費用の負担のことであり、養育費の定めとは、両親の扶養義務の分担についての定めです。
別居や離婚に伴って一方の親が未成熟な子供を引き取って養育することになった場合は、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。
2.養育費の額・支払方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。
お互いの収入や財産、これからの見通しなどを考慮して協議します。
3.しかし、双方の主張にへだたりがあり合意が難しい場合は、客観的で合理的な算定基準が必要となります。
4.養育費という言葉は法文上にはありませんが、夫婦間の扶助義務、婚姻費用分担、離婚後は監護費用が根拠となるといわれています。
また、養育費の算定基準も規定にはないため、子どもの数・年齢・それぞれの親の年齢を考慮した算定表を、家庭裁判所が作成しています。
5.養育費は、食費や教育費など子どもが成長していくうえで日々生じるものであり、分割払いが原則です。
従って、不払い時の「期限の利益喪失条項」なども付することはできません。 ただし例外的に、一時払いとして定める場合には、期限の利益喪失条項を付することも可能です。
6.両親の間で「養育費不支給の合意」を定めても、扶養を受ける権利を処分することは禁止されているので(民法881条)、後で無効とされる可能性があります。
また、「養育費不支給の合意」があっても、子ども自身が養育費の請求をすることは妨げられません。(判例)
7.養育費についての取り決めは、長年にわたる支払いとなることが多いため、口約束ではなく、書面にして合意をしておく必要があります。
8.できるだけ「公正証書」にして、「約束を守らない場合は、強制執行をしてもかまいません」という「強制執行認諾条項」をつけておけば、支払が滞った場合に裁判をしなくても、支払義務者の給料を差押えることが可能となるので、養育費の支払い確保に有効となります。 面接交渉権
面接交渉権
1.面接交渉権とは、「離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった者
が、その未成年の子供と面接、交渉する権利」をいいます。
子の監護をしている親は、これに協力しなければなりませんが、どの程度、どのように協力しなければならないかは、明文の規定はありません。
2.重要なのは、「子の福祉」です。実際には、子どもの年齢によるところが多く、面接交渉に子供自身がどのような意思や意見をもっているか、子の心身にどのような影響を及ぼすかという点は、最も重要な要素です。
離婚に際して面接交渉についての取り決めをするときは、子の福祉を最優先に考え、それを害することのないように配慮することが大切です。
調停離婚と裁判離婚

参考に、調停離婚と裁判離婚について、
説明しておきます。 調停離婚
調停離婚
1.夫婦2人の話し合いで離婚の合意ができないときは、家庭裁判所で調停の申立てができます。
調停申立の手続きは、家庭裁判所の職員がていねいに教えてくれるので、個人でも簡単にできます。
2.法律で、この調停手続きをとらずに、いきなり裁判離婚の訴訟を起こすことはできないことになっています。(調停前置主義)
3.調停では、当事者の夫婦、調停委員、裁判官が話し合いを行います。
大体月1回のペースで開かれ、当事者一方だけが部屋に呼ばれ、事情を聞かれたり、主張も聞いてくれます。また、相手の主張も説明されます。
1人づつ交代で部屋に入り話しをするわけですから、待ち時間も多く、時間がかかります。また、月1回ですから、半年ぐらいはかかると思った方がいいです。
4.裁判所といっても、堅苦しい雰囲気ではありません。
調停は、個人で手続きができるし1人で主張もできますから、便利な制度ですが、相手側に弁護士がついていれば、当然主張の仕方がうまいわけで、不利になる可能性が高くなります。
自分1人では主張が通らないと判断したら、早めに弁護士を同行すべきです。
5.調停が成立し、その内容が調停調書に記載されると確定判決と同じ効力をもち、その時点で離婚が成立します。
6.この調停調書を添えて、市区町村の戸籍課に離婚届を提出します。 裁判離婚
裁判離婚
1.調停による話し合いがつかず不調に終わったときは、裁判による離婚を提起することができます。
(※ 実際にはあまりありませんが、調停成立の見込みはないが、審判が相 当であるという事案では、裁判所が職権で調停に代わる審判をすることが あります。これが、「審判離婚」です。)
2.裁判離婚では、民法770条に定められた離婚原因が必要で、訴えを起こす側は、その訴訟において、離婚原因の存在を主張・立証しなければなりません

(民法770条1項各号)
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ただし1から4の事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻 を継続すべきと考えるときは、離婚を認めないことがあります。
(民法770条2項)
公証人手数料

公正証書の離婚給付契約における、公証人手数料について説明します。
1.協議離婚の届出に際して合意した財産分与の取り決め、慰謝料または未成年の子の養育費の支払いを公正証書にする場合は、財産分与、慰謝料と養育費とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
2.ただし、養育費の支払いは、賃料と同じく定期給付にあたるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額となります。